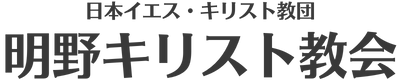| 2024年1月28日 第三主日礼拝 説教「むち打たれた神」 ヨハネの福音書19章1-16a節 |
また、心が痛む説教題にしてしまいました。語るのもつらい箇所です。けれどもやはり目をそらしてはならないとも思うのです。十字架こそが神の私たちへの愛のクライマックスなのですから。
【この人を見よ】
他の福音書では、イエスのむち打ちは、十字架の死刑判決の後です。ところが、ヨハネは裁判の始まる前に、ピラトの命令で行われたと記します。ピラトはイエスが無実だと思っていましたから、むち打たれボロボロになったイエスの姿をユダヤ人たちに見せ、「もう十分だ」と思わせて、イエスを釈放しようとした。これがヨハネの言おうとしているところです。ところがユダヤ人たちは「十字架につけろ。十字架につけろ」(6a)と叫びます。ピラトは「私にはこの人に罪を見出せない。」(6c)と言い、「ピラトはイエスを釈放しようと努力した」(12a)のですが、結局は十字架刑に同意してしまったのでした。
ピラトの言葉「見よ、この人だ。」(5c)は、もともとは「このみじめな男をみろ、ボロボロじゃないか。十字架に架けてもしようがないから、ゆるしてやれ」という意味でした。けれどもキリスト教会はピラトの言葉に、ピラトが思ってもいなかった真実を見出したのでした。それをよく表すのが、新聖歌99「馬槽の中に」です。4節「この人を見よ この人こそ 人となりたる 活ける神なれ」。この人を見よ、このボロボロのみじめな男を。なんとこの男は神!ぼろぼろの神、むち打たれた神。私たちのためにボロボロになることをいとわない神、私たちのためにむち打たれることをいとわない神。この神を見よ、この神を受け入れよ、この神とともに生きよ、と。
【見よ、神の子羊】
いよいよ主イエスの裁判が始まりました。ヨハネはここで「その日は過越の備え日で、時はおよそ第六の時(正午)であった。」(14b)と記します。過越の備え日、すなわち過越の小羊を屠り、過越の食事の準備する日の午後に、主イエスは十字架に架けられたのでした。まさに過越の小羊が殺される時間。思い出されるのは、かつてバプテスマのヨハネが主イエスについて語った「見よ、神の子羊」(ヨハネ1:36)です。ヨハネは一貫して、主イエスは過越の小羊だと記します。過越の小羊によって、イスラエルの民のエジプトでの奴隷の苦しみからの解放、救いが実現しました。そのように、主イエスの十字架と復活によって私たちの救いも実現したのでした。
【救いの四つ顔 その1「和解」】
主イエスが十字架と復活によってなしとげてくださった恵みは巨大です。私たちにはその全体を知ることはできません。それでも教会は、二千年の歴史を通してさまざまな恵みを発見してきました。そのうちの主な四つを、一年12回で聖書を読む会のテキスト「聖書は物語る 一年12回で聖書を読む本」に載せています。今日はそのうちの第一番めのものを取り上げることにしましょう。
それは、「神と人との交わりの回復の十字架(和解)」です。神が人を創造した目的は、人と愛し合い、喜び合うため。けれ ども、この愛の関係は人が神に背を向けたために損なわれてしまいまし た。これまで何度も、最初の人の名前「アダム」は固有名詞ではなく、「人」 という意味の普通名詞だと申し上げてきました。ですから聖書によれば 人はみな神に背を向けており、神との関係が損なわれています。神には、このままで私たちを放っておくことができません。そうするには神はあまりに愛に満ちているからです。けれども、私たちにはそんな神の愛がわかりません。目で見ることがで きるならば、わかるかも知れないのですが……。いったい、どこで神の 愛を見ることができるのでしょうか。それが十字架です。十字架に架けられたイエスは神。父なる神とは区別される子なる神。人となった神です。 この神が十字架の上で発した言葉の一つが、「父よ。彼らをお赦しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです」( ルカ 23:34) で す。自分の苦しみを省みず、人のためにとりなす神の姿がここにありま す。イエスのとりなしは、自分を十字架に架けたユダヤ人やローマ人の ためだけではありません。神に背を向けているすべての人のためのとり なしです。このとりなしの愛を知るとき に、人は心を開いて、神との関係を回復 することを望み始めます。和解はすでに 神から差し出されています。神の愛の迫りを知るときに、人は心を開き始めます。その和解を受け入れ始めるのです。強いられてではなく、愛にとかされて。 「神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた」(マルコ 15:38)とあります。 この幕とは神殿の聖所と至聖所を隔てていた幕です。この幕の中の至聖 所には大祭司が一年に一回入る以外はだれも入ることは許されていませんでした。そこは神が人に会う場所とされていました。けれどもイエス の十字架の死と同時に隔ての幕は裂かれました。このことは神と人との 和解が可能になったことの象徴です。(同書87-88頁)
罪を赦すばかりか、和解さえも望み、共に生きてくださる神。人となりたる活ける神をこの朝も喜びます。